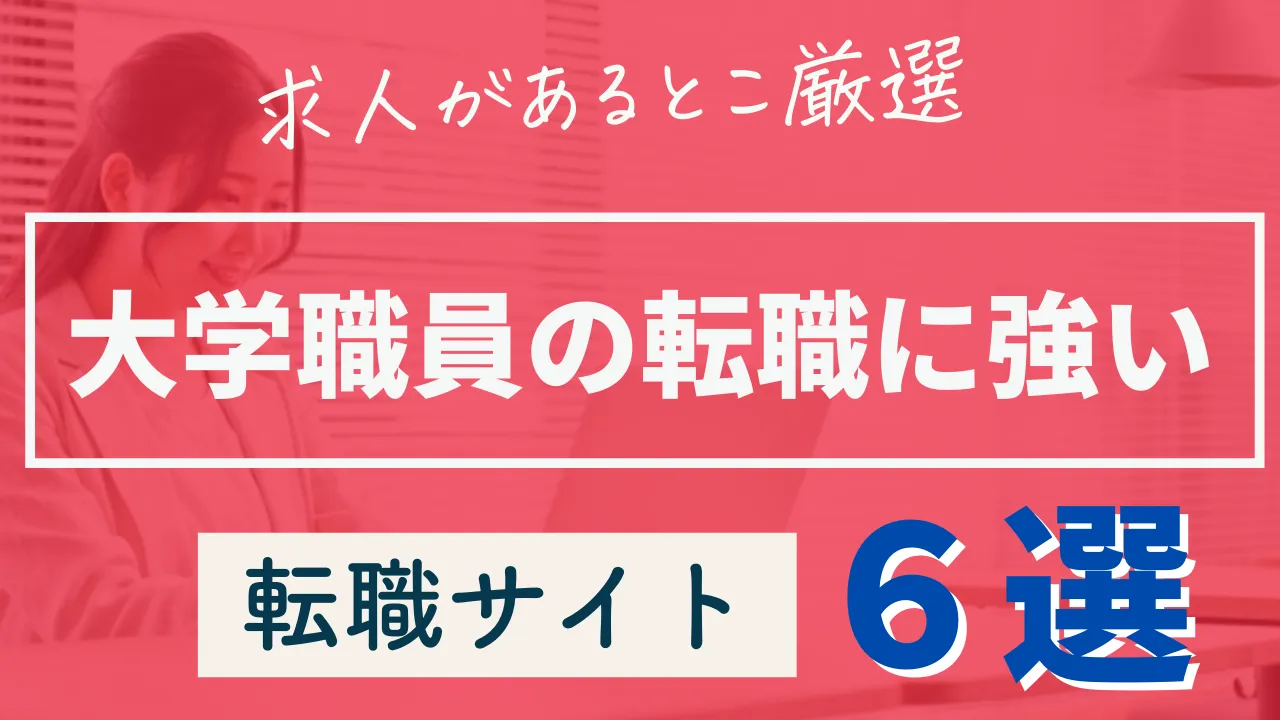前回の「カリキュラム①自分を知る-自分史の作り方-」では、お疲れさまでした。
はじめてのワークで大変だったと思います。
短期間で集中してワークに取り組んだ後に、コーチとの個別オンライン面談をしたことで、自己理解も深まったのではないでしょうか。
まだ1週間の理解度調査※に回答していない場合はすぐに以下のフォームから回答してください。
※コーチとの個別オンライン面談が終わるごとに回答が必要です。
\ 毎回のオンライン面談終了後に回答してください /
それでは今週のワークも頑張りましょう!
これからの1週間の流れは以下のとおりです。
-これからの1週間の流れ-
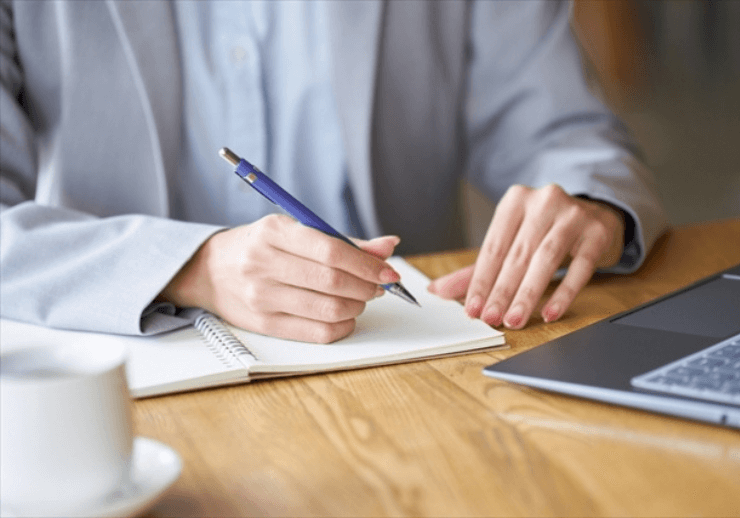
このページを見ながらワークに取り組む
カリキュラムごとに課題が出ます。このページにある専用動画・Webコンテンツを観ながら、まずはあなた自身でワークに取り組みましょう。
コーチとの個別オンライン面談
これからあなたが取り組むワークが完成したらコーチとオンライン面談を行います。疑問点や課題を解決しながら内容をブラッシュアップしましょう。

ワークの趣旨を理解しよう
以下ページでは、今回取り組むワークの趣旨を分かりやすく解説しています。
どんなことを意識してワークに取り組めばいいのかを理解しましょう。
カリキュラム②自分を知る(職務経歴書を完成させる)
自分史をベースに職務経歴書を完成させる
 コーチ
コーチ前回の個別オンライン面談でコーチからのアドバイスをもとに自分史に追加や修正を行ってから今回のワークに取り組みましょう!
今回は、大学職員の書類選考で提出を求められる職務経歴書を実際に書いてみます。
本番の選考でもすぐに提出できるように今週で仕上げましょう。
以下の順番でワークを進めてください。
teamsで運営事務局からの案内を確認して、ワークシート(職務経歴書)をダウンロードしよう。
記入例では、お手本となる職務経歴書を限定公開しているので参考にしてください。
ただ闇雲に職務経歴書を書いても大学職員の書類選考は通過しません。
まずは、書類選考を通過するための職務経歴書の書き方をマスターしてからワークに取り掛かりましょう。
職務経歴書を書く時にやってはいけないこと



職務経歴書を書く時はどんなことに気をつければいいの?



以下の減点される書き方にならないように気をつけましょう!
面接に呼んでもらうためには、面接官が職務経歴書を読んだときに「減点されない」ことが最初のステップです。
どれだけ良い内容を書いたとしても以下の減点ポイントがあると書類選考は通過しないので注意しましょう。
- 誤字や脱字がある
- 顔写真の印象が悪い
- 数字の全角・半角がバラバラ
- 一文が長くて読みにくい
- 西暦・和暦が混ざるなどフォーマットが統一されていない
- 職歴に早期離職・空白期間がある
職務経歴書を書くにあたって、減点されるような書き方をしていないか注意しましょう。
誤字や脱字、数字の全角・半角などはていねいに読み返せば、必ずミスを防ぐことができる項目です。
運営事務局に今回のワークを提出するときは、本番の書類選考に提出するつもりでしっかりチェックしてから提出しましょう。
職務経歴に早期退職や空白期間はありませんか?



早期退職や空白の期間がある場合は書類選考が通りにくいです。
職歴にコンプレックスを抱えている方には大変申し訳ないですが、このカリキュラムは「大学職員に就職する」ことが目的なので、まずは現実を把握して欲しいと思います。
大学職員の採用は中途採用や新卒採用のどちらも長期間にわたって活躍できる人を採用したいと考えています。(応募条件に35歳以下などの年齢制限があるのはそのため)
また、中途採用では即戦力となる人材を求めているのでこれまでの職歴やキャリアを重視する傾向があります。
「うちの大学でも早期退職をする可能性があるかな、空白期間があるけど即戦力として活躍できるだろうか?」という不安が面接官の脳裏にあるため書類選考が通過しづらくなっています。



早期退職・空白期間がある場合はどうしたらいいの・・・?



早期退職・空白期間の理由を書いて対策しましょう!
職歴に早期退職や一定期間の仕事をしていなかった空白の期間がある場合は、職経経歴書の備考欄や余白に「早期退職や空白の期間がある理由」を書くようにしましょう。
面接官が「採用を見送りたいと感じるポイント」の理由を先回りしてこちらから説明書きすることで、すぐに採用見送りとなっていたはずの職務経歴書が他の部分まで見てもらえるようになるかもしれません。
理由を書けば、採用見送りを必ず防げるというわけではありませんが、少しでも可能性を高めるためにできることはすべてやりましょう。
職歴要約は「興味を持ってもらう」ための文章を書こう



職歴要約ってどんなことを書けばいいの?
職歴要約は、自分の職歴を要約する内容を書くのではなく、面接官が読んだときに興味を持ってもらえるような内容を書きましょう。



求める人物像とマッチしていれば興味がわいてくる!
これまでの職歴を振り返りながら、大学職員の求人で求められる人物像をアピールできる内容を書きながら、職歴をまとめてみましょう。
- 当事者意識をもって主体的に業務に取り組むことができる人
- まわりと力を合わせて業務を進めることができる人
- さまざまな業務やマルチタスクにも柔軟に対応できる人
職務要約はあくまで要約なので、あまり長文になりすぎないように文字量には気をつけましょう。
端的に自分の職歴を説明しながら、これまでの経験や人柄を伝えることを意識してください。
職歴は初めて読む人がイメージできる内容で書こう
職務経歴書の「職歴」には、勤務先や仕事をしていた期間などの基本情報に加えて、どのような業務を行っていたかを記載する必要があります。
職歴を記載する場合は、全くその業界のことを知らない人が初めて読んでも分かるように記載しましょう。



以下の要素を入れるとわかりやすくなるよ!
- 人数やエリアなどの規模感
- 自分の役職や担当業務
- 業務の目標や目的



職歴はどんな順番で書けばいいの?
職務経歴書に記載する職歴の書き方は主に3つの方法があります。
- ①時系列順で書く方法(古い経歴から書く)
-
新卒の頃から社会人としてキャリアをスタートした順番に書く方法です。社会人キャリアの順番で上から下に読むことができるので、シンプルで読みやすい特徴があります。
一方で、職歴が多い場合には古い順番で長々と記載することになるので最近の業務経験が伝わりづらくなるデメリットもあります。 - ②逆の時系列順で書く方法(新しい経歴から書く)
-
直近の職歴から順番に書く方法です。中途採用の場合は最近の業務経験や身につけたスキルをアピールできるので、即戦力としてのアピールがしやすい特徴があります。
一方で、これまでのキャリア全体を掴むためには下から上にかけて読み直す必要がある点がデメリットです。 - ③アピールしたい順番で書く方法
-
自信のある経験ごとに書いたり、アピールしたい強みやスキルごとに書いたりする方法です。いろいろな業務経験を通じてアピール項目が伝わりやすくなる特徴があります。
一方で、これまでの職歴やキャリアの流れが分かりづらいという点がデメリットです。



大学職員の中途採用なら①時系列順で書こう!
大学職員の中途採用では「即戦力」が求められます。
他にも多くの人々とチームで働くこと、人事異動があれば全く異なる仕事をすることから人間性やこれまでの業務経験について面接官は見ています。
即戦力であることを伝えるためには、①時系列順で書くのが最もおすすめです。
- 志願者の職歴とキャリアが分かりやすい
- 面接官が見慣れているので内容が入ってきやすい
- 時系列に沿って今の強みをアピールしやすい
面接官は職務経歴書を上から下に目線を動かしながら読んでいきます。
そのため、転職などで職歴が多い場合は最初の職歴を分量多く書きすぎて、比重が高くなりすぎないように気をつけましょう。
面接官が即戦力として判断しやすいポイントは直近の経歴なので、その点は注意が必要です。
活かせる経験・知識・スキルは厳選したものを書こう
大学職員の書類選考では、職務経歴書だけでなくエントリーシートの提出も求められます。
大学が指定するエントリーシートの書式では、志望動機や頑張った取り組みを記述する欄があり、詳しい内容はエントリーシートで書くことができます。
そのため、職務経歴書に記載する「活かせる経験・知識・スキル」の欄には厳選した内容を端的に書くようにしましょう。
職務経歴書は志願者のキャリアだけでなく、人物の全体像をおおまかに把握するための書類です。
自分という人柄を伝えるための書類になるようこれまでの経験や職歴を振り返って書いてみましょう。



うまく書けない場合はどうしたらいい?



最初から短く書こうとせず、まずは文量も項目も絞らず書いてみよう!
1週間のさいごにコーチと行うオンライン面談のなかで内容をブラッシュアップ、深掘りしていくので、最初から無理やり短く書こうとせずに、まずは文量と項目をしっかり書き出しましょう。
そのうえで、自分が一番使いたい部分を決めて、コーチに相談してください。
オンライン面談のなかでコーチと一緒に納得できる内容に仕上げていきましょう。
取得した資格は大学職員として活かせるものを書こう
取得した資格を記載する欄では、大学職員になっても活かせる資格や汎用性のある資格を中心に書きましょう。
大学職員になる場合、「この資格があると有利になる!」というものはありませんが、大学職員になってからも活かしやすい資格はあります。
資格をたくさん持っているからといって、むやみやたらにすべての資格を記載するのはやめましょう。



「資格欄の意図を考えられない人だな」とかえってマイナスに働くことがあります。
- 日商簿記 1級~3級
-
日商簿記は簿記の考え方を知るうえで欠かすことができない資格です。企業会計と学校会計では多少の違いはあるものの、仕訳の考え方などは同じなので、大学の財務部が行う決算業務や各部課室の予算管理などで役立てることができます。
- MOS(Microsoft Office Specialist)
-
大学職員は業務の約8割をパソコンを使って行います。(交渉・調整業務を除く)MOSは現場レベルのPCスキルを証明するための資格として効果があります。
- 司書資格
-
大学の図書館勤務で役立つだけでなく、教育業界への深い理解を示すことができます。アカデミックライブラリアンとして教育支援センターや学術情報センターなどの勤務で役立ちます。
- TOEIC(600点~)
-
英語対応が必要な場面で活かすことができます。国際交流センターでの業務だけでなく、教務課の教員対応や留学生対応の場面で効果を発揮するでしょう。
- ITパスポート
-
基本情報技術者ほど難易度が高くない資格ですが、取得していればITに関する基礎を理解した上で、ITリテラシーを有した人物であることを証明できます。
- キャリアコンサルタント
-
キャリアセンターでの業務において役立ちます。学生のキャリア選択をサポートすることができるため、キャリア面談や就活対策のコーディネーターとしても活かせるでしょう。
- ファイナンシャルプランナー
-
FPは経済社会の基本を学ぶことができるので、奨学金業務や寄付金業務で活かすことができます。
自分史を使って自己PRを書いてみよう
前回のワーク①で作った自分史を見ながら、自己PRを書いてみましょう。
大学職員を目指す中で自己PRをする目的は何だと思いますか?



自分の優秀さをアピールするためではありません!
大学職員の中途採用では、条件にマッチした人材を採用したいと考えています。
求人に対してスキルが足りないと判断されると業務が回らず、周りにしわ寄せがくるため採用されません。
極端にハイスペックすぎても、1年で辞めてしまうだろうと判断されて採用されません。
実際の求人を見ながら自己PRを書いてみよう
それでは実際の求人を見ながら、自己PRを書いてみましょう。
求人を見る時には以下の項目を探して、面接官が知りたいポイントを押さえて自己PRすることが大切です。
- 求める人物像
- 応募に必須な条件
- 歓迎する条件



求人はどうやって探したらいいの?
大学職員の求人がよく掲載されているサイトは以下の記事で紹介しているので、「どこから求人を探したらいいか分からない」ときは参考にしてください。



今のタイミングでエントリーできなくても良いので、まずは実際の求人を見て求める人物像のイメージを掴んでください!
以上で今回のワーク「職務経歴書」は完成です。
完成したワークをteamsから提出してください。
\ 運営事務局から付与されたID,パスワードでログインしてください /
次回はコーチとのオンライン面談なので、今回の職務経歴書をブラッシュアップして、いつでも求人応募で提出できるように仕上げましょう。